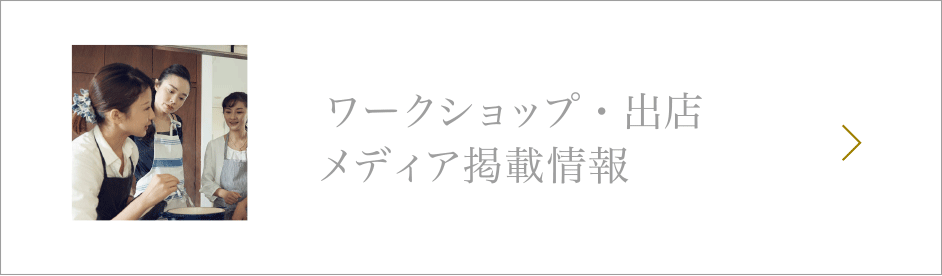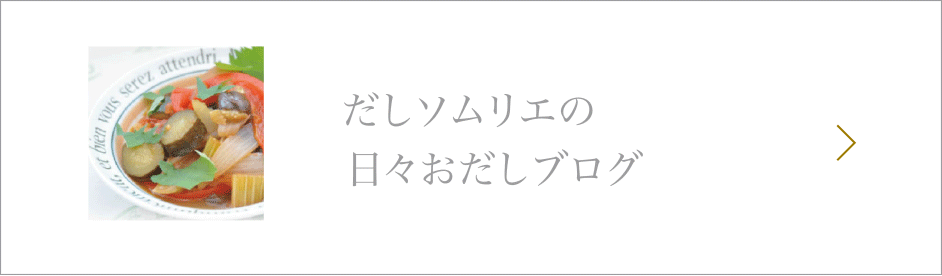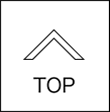2025・09・02
うま味とは?
皆さん、「うま味」という言葉を聞いたことはありますか?
日本の「出汁」文化から世界に広まったこの言葉は、今や世界中のシェフや料理好きが注目する”おいしさの秘密”です。
「甘い」「しょっぱい」と違い、一言で説明するのが少し難しい「うま味」。
今回の記事では、この不思議で奥深い味覚の正体に迫ります!

〇「うま味」-5番目の基本味
「旨味(うまみ)」が世界で知られるようになったきっかけは、1908年に日本の化学者・池田菊苗博士が、昆布だしの中からその味の成分(グルタミン酸)を発見し、それを「うま味」と名付けました。
その後、研究が進み、「うま味」は甘味・酸味・塩味・苦味に並ぶ、人間が感じる5番目の「基本味」として世界的に認められました。
日本の食文化から生まれた言葉が、今や世界共通の言葉になっているのは、とても興味深いですよね。

〇「うま味」とはどんな味?
他の味と違って、はっきりと「これだ!」と表現するのが難しい「うま味」。
私は、うま味とは「料理全体の味を支える土台であり、味わいに深みとまとまりを与えてくれる存在」だと考えています。
うま味の特徴を言葉にするなら、こんな表現がぴったりです。
まろやかで、持続性がある、塩味のように舌をピリッと刺激するのではなく、舌全体を優しく包み込むように広がり、後を引くような心地よい余韻を残します。
料理にコクと豊かさを与える単体で強い味を主張するわけではありませんが、他の味と合わさることで、料理全体の満足感をぐっと高めてくれます。
日本では、うま味を最もわかりやすく感じられるのが「出汁」です。
塩や砂糖を沢山足さなくても、飲むだけでじんわりと広がる「おいしさ」と、心がホッとするような感覚。それこそが、まさにうま味なのです。
しかし、うま味は日本料理だけのものではありません。
日本の出汁では、「魚介」「椎茸」「昆布」が主流ですが、完熟トマトやパルメザンチーズ、きのこ、熟成肉など、世界中の様々な食材が出汁となり、豊富なうま味が含まれています。実は、皆さんが普段食べている料理にも、うま味は隠れているのです。
ぜひ、日々の食事の中でこの「料理の土台となる優しい味わい」、うま味を探してみてはいかがでしょうか。
日本の「出汁」文化から世界に広まったこの言葉は、今や世界中のシェフや料理好きが注目する”おいしさの秘密”です。
「甘い」「しょっぱい」と違い、一言で説明するのが少し難しい「うま味」。
今回の記事では、この不思議で奥深い味覚の正体に迫ります!

〇「うま味」-5番目の基本味
「旨味(うまみ)」が世界で知られるようになったきっかけは、1908年に日本の化学者・池田菊苗博士が、昆布だしの中からその味の成分(グルタミン酸)を発見し、それを「うま味」と名付けました。
その後、研究が進み、「うま味」は甘味・酸味・塩味・苦味に並ぶ、人間が感じる5番目の「基本味」として世界的に認められました。
日本の食文化から生まれた言葉が、今や世界共通の言葉になっているのは、とても興味深いですよね。

〇「うま味」とはどんな味?
他の味と違って、はっきりと「これだ!」と表現するのが難しい「うま味」。
私は、うま味とは「料理全体の味を支える土台であり、味わいに深みとまとまりを与えてくれる存在」だと考えています。
うま味の特徴を言葉にするなら、こんな表現がぴったりです。
まろやかで、持続性がある、塩味のように舌をピリッと刺激するのではなく、舌全体を優しく包み込むように広がり、後を引くような心地よい余韻を残します。
料理にコクと豊かさを与える単体で強い味を主張するわけではありませんが、他の味と合わさることで、料理全体の満足感をぐっと高めてくれます。
日本では、うま味を最もわかりやすく感じられるのが「出汁」です。
塩や砂糖を沢山足さなくても、飲むだけでじんわりと広がる「おいしさ」と、心がホッとするような感覚。それこそが、まさにうま味なのです。
しかし、うま味は日本料理だけのものではありません。
日本の出汁では、「魚介」「椎茸」「昆布」が主流ですが、完熟トマトやパルメザンチーズ、きのこ、熟成肉など、世界中の様々な食材が出汁となり、豊富なうま味が含まれています。実は、皆さんが普段食べている料理にも、うま味は隠れているのです。
ぜひ、日々の食事の中でこの「料理の土台となる優しい味わい」、うま味を探してみてはいかがでしょうか。